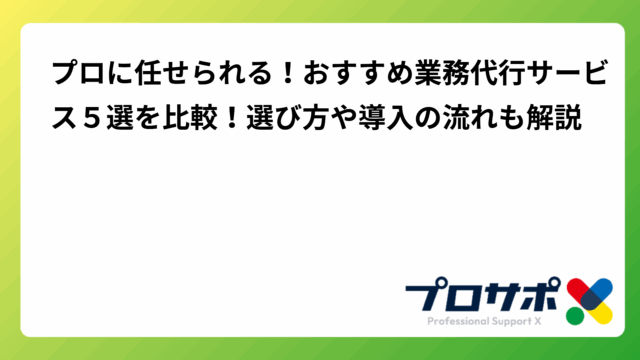近年、経理や人事などの定型業務を効率化する「バックオフィス自動化ツール」が注目されています。人手不足や属人化の課題を抱える中、作業時間を大幅に削減できる点が魅力です。本記事では、自動化ツールの種類や導入効果、代表的な製品の比較までわかりやすく解説します。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
バックオフィス自動化とは?業務改善が進む理由

バックオフィス業務の種類と課題
バックオフィス業務とは、企業の経営を支える間接業務全般を指します。代表的なものには、経理・財務、人事・労務、総務、法務などがあります。これらの業務は、顧客との直接的な接点を持つフロント業務とは異なり、社内の管理・運営を円滑に進めるために欠かせない役割を果たしています。
しかし、バックオフィス業務の多くは、帳簿入力や勤怠管理、書類作成、データの照合など、手作業でおこなわれている場合が多く、また、「定型的」「繰り返し型」の作業が中心です。
このため、作業時間の増加や人的ミス、業務の属人化が問題となりやすく、効率化が求められる領域でもあります。
なぜ今、自動化が注目されているのか?
バックオフィス自動化が注目を集めている背景には、いくつかの社会的・経済的な要因があります。
まず、人手不足の深刻化です。特に中小企業では限られた人材で多くの業務をこなす必要があり、担当者に過度な負担がかかっています。次に、コロナ禍をきっかけとしたリモートワークの普及です。
従来は紙ベースで行っていた業務も、クラウドやデジタル技術を活用してオンライン化する必要が出てきました。
さらに、政府が推進する「働き方改革」や「中小企業のデジタル化支援」などの施策により、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、業務の自動化に取り組み始めています。
このような時代の流れの中で、バックオフィスの自動化は単なる業務効率化ではなく、「組織の競争力を高めるための重要戦略」として位置づけられつつあります。
自動化できる業務とその効果
経理・会計業務(例:請求書処理・仕訳入力)
経理・会計業務は、定型的な処理が多く、自動化による効果が非常に大きい分野です。たとえば、請求書の受領から支払処理、仕訳入力、帳簿記帳に至る一連の業務は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やクラウド会計ソフトを活用することで、大幅に効率化できます。
OCR(文字認識技術)を用いた請求書の自動読み取りや、AIによる仕訳候補の自動提案など、人の手を介さずに処理できる部分が増え、担当者の確認業務だけに集中できる体制が整います。
人事・労務業務(例:勤怠管理・給与計算)
人事・労務業務では、従業員の勤怠情報の収集と集計、残業管理、給与計算などが主な対象です。これらの業務もまた、クラウド勤怠システムや給与計算ソフトの導入によって自動化が進んでいます。
例えば、勤怠情報をクラウド上で一元管理し、所定のルールに基づいて自動的に給与額を算出する仕組みにすることで、煩雑なチェック作業や集計ミスを防げます。また、年末調整や社会保険手続きなども、クラウドツールの導入で大幅な省力化が可能です。
総務・庶務業務(例:備品管理・契約書管理)
総務部門では、社内備品の発注管理や契約書の保管・更新といった、地味ながら重要な業務が数多くあります。これらもクラウド型のワークフローシステムやドキュメント管理ツールを導入することで、作業の標準化と効率化が図れます。
たとえば、契約書の電子化と自動リマインド機能を持つ管理システムを導入することで、更新漏れの防止や書類探しの時間削減につながります。
自動化による業務時間の削減効果とは?
自動化ツールを導入した企業の多くは、30〜50%程度の業務時間削減を実現しています。たとえば、経理業務においては、手作業で4時間かかっていた月次処理が、クラウド会計ソフト導入後には1時間以内で完了したというケースもあります。
また、処理スピードの向上だけでなく、ヒューマンエラーの減少や、業務の属人化解消といった副次的効果も大きなメリットです。自動化によって空いた時間を、分析業務や戦略立案といった「本来担うべき価値の高い仕事」に充てられる点も、多くの企業が評価しています。
バックオフィス自動化ツールの比較ポイント
RPA型/AI型/クラウド型の違い
自動化ツールは大きく分けて「RPA型」「AI型」「クラウド型」に分類されます。それぞれの特性を理解することが、適切なツール選定の第一歩です。
- RPA型(Robotic Process Automation)
人間がパソコン上で行っている定型作業をソフトウェアロボットが代行します。既存の業務フローを変えずに導入できる点が魅力です。
例:UiPath、BizteX cobitなど。
- AI型
AI(人工知能)を活用して、学習や推論による判断を含む業務を支援します。特に自然言語処理や画像認識、データ分析を必要とする場面で有効で
例:AI 、OCR、ChatGPT APIの活用など。
- クラウド型
Web上のプラットフォームを通じて、会計・人事・勤怠などの機能を提供するSaaS型のツールです。導入や管理が容易で、リモートワークにも適しています。
例:freee、マネーフォワードクラウド、SmartHRなど。
自社に合った選定のポイント

ツール選定時には、以下のような観点をバランス良く評価することが重要です。
- 対応業務の範囲:自社が自動化したい業務(経理・人事・契約管理など)にマッチするか。
- 操作のしやすさ:現場の担当者が直感的に扱えるUI/UXか。ノーコード対応か。
- 導入・運用コスト:初期費用や月額費用、オプションの有無。
- サポート体制:導入支援やヘルプデスクの充実度。中小企業向けのサポート有無。
- スモールスタートの可否:小規模から始めて段階的に拡張できるか。
特に中小企業の場合、「業務にフィットするか」「導入後のサポートがあるか」の特に2点は重視される傾向があります。
セキュリティ・連携性のチェックも重要
バックオフィスツールでは、従業員情報や財務データなどの機密情報を扱うため、セキュリティ面の信頼性は非常に重要です。たとえば以下のような点を確認しましょう。
- データ通信の暗号化(SSL対応)
- アクセス権限の細分化機能
- 外部サービス(会計ソフト、CRMなど)との連携可否
- クラウド上のデータ保全体制(サーバーの所在・稼働率など)
これらの観点を踏まえて比較検討することで、業務効率と安心感を両立できるツールを選定できます。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
最新バックオフィス自動化ツールおすすめ10選
ここでは、数あるバックオフィス自動化ツールの中から、用途別・業務別に導入しやすい代表的なソリューションを10個厳選してご紹介します。
1. Power Automate(Microsoft)
Microsoftが提供する自動化プラットフォーム。ノーコードで業務プロセスを自動化でき、OutlookやExcel、SharePointなどOffice製品との親和性が非常に高い。Microsoft 365ユーザーにおすすめ。
2. UiPath
本格的なRPAツールとして、複雑なバックオフィス業務の自動化に対応。視覚的なフロー設計が可能で、業務に合わせた柔軟な構築ができる。大企業から中堅企業まで幅広く導入されている。
3. BizteX cobit
日本国内の企業向けに最適化されたクラウドRPA。ブラウザ操作の自動化に強く、SaaS業務との相性がよい。初期費用を抑えたい中小企業にも人気。
4. 楽楽精算・楽楽明細(RAKUS)
経費精算や帳票発行などの業務を自動化できるクラウドツール。交通費申請や請求書処理を簡略化でき、経理部門の工数を大幅に削減可能。
5. SmartHR
労務手続きのペーパーレス化を実現するクラウド人事労務ソフト。入社手続きや雇用契約、社会保険関連の自動処理などに対応。従業員情報の一元管理が可能。
6. マネーフォワードクラウド
会計・請求書・経費精算・給与など多様なバックオフィス業務に対応するクラウドサービス。自動仕訳や連携機能が豊富で、税理士との連携もスムーズ。
7. freee
クラウド会計ソフトの先駆け。直感的なUIとシンプルな操作性が特徴で、会計知識がなくても導入しやすい。個人事業主や中小企業に人気。
8. jinjer
人事管理から勤怠、給与、労務まで対応するオールインワン型のクラウド人事ツール。モバイル対応に優れ、現場でも使いやすい。
9. バクラクシリーズ(LayerX)
AI OCRを活用した請求書処理・契約書管理などを自動化。クラウドでの電子帳簿保存にも対応し、インボイス制度や電帳法にも適応。
10. Google Apps Script(GAS)
Google Workspaceユーザー向けに、スプレッドシートやGmail、カレンダーなどを自動連携・処理できるスクリプト。ノーコード感覚で活用でき、無料で始められる点が魅力。
各ツールには得意分野や導入規模に応じた特性があります。自社の業務課題と照らし合わせて、最適な組み合わせを検討してみましょう。
導入時の注意点と成功のコツ
社内業務の可視化と棚卸しが第一歩
自動化ツールを導入する前にまず必要なのは、自社の業務内容を可視化し、どの作業が自動化に適しているかを明確にすることです。手作業が多く、ルール化されている業務ほど自動化の効果が出やすいため、業務をフローチャートや一覧表にまとめて整理しましょう。
これにより、導入対象の優先順位をつけやすくなり、投資対効果も見えやすくなります。
ツール導入と並行して業務フローの見直しを
自動化ツールをそのまま既存業務に適用しようとすると、非効率な作業まで再現してしまう恐れがあります。そのため、導入時には「この業務の目的は何か」「重複や無駄はないか」など、業務フローそのものを見直すことも重要です。
業務改革(BPR:ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)とセットで進めることで、単なる「ツール活用」に留まらず、抜本的な業務改善が可能になります。
運用定着を支援する社内教育・研修も重要
ツールの効果を最大限に発揮するには、社内に定着させることが欠かせません。とくに現場スタッフが日常的に操作する場合は、導入直後の研修やマニュアル整備、定期的なフォロー体制が求められます。
また、現場からのフィードバックを吸い上げて、設定の見直しや業務の再構築に活かすことで、継続的な改善サイクル(PDCA)を回しやすくなります。
まとめ|自社に最適な自動化ツールで業務時間を半減しよう

バックオフィスの自動化は、単なる作業効率の向上にとどまらず、企業全体の生産性や競争力を底上げする有効な手段です。
本記事では、自動化が可能な業務の具体例から、ツールの選定ポイント、代表的なソリューション、導入時の注意点までを解説してきました。
自社にとって最適なツールを選ぶためには、まず業務の棚卸しを行い、課題や改善ポイントを明確にすることが不可欠です。
その上で、目的に合ったツールを比較検討し、導入後の定着・活用を見据えた運用体制を整えることで、着実な業務改善につながります。
近年では、無料トライアルやスモールスタートに対応したツールも多く提供されています。まずは小さく始めて、社内の課題解決に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
経理・人事・総務・電話対応など、プロサポXは経営者の業務負担を減らす仕組みを整えています。
単なる外注ではなく、経営者が本来の業務に専念できるよう、継続的なサポート体制を構築しています。必要な時にすぐ相談・依頼できるのが特長です。
継続的なサポート体制(LINEと専門スタッフ連携)
- LINEから業務相談や申込みが可能
- 経理・人事・総務などの代行に対応
- 依頼後も継続的にサポート&報告
依頼後も担当スタッフが継続してフォローする体制があり、初めての方でも安心して利用できます。
まずはサービス内容をチェックして、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。