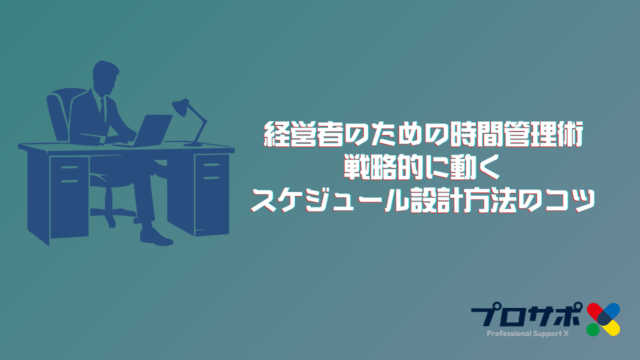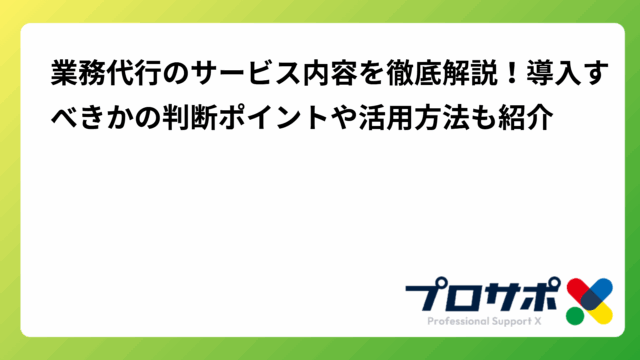人手不足やコスト増を背景に、「バックオフィス代行」への関心が高まっています。経理や人事などを外部に任せることで、社内ではより柔軟で効率的な働き方が可能になり、業務全体のバランスを整えることにもつながります。本記事では、選び方や導入のポイント、おすすめのサービスをわかりやすく紹介します。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
バックオフィス業務代行とは?
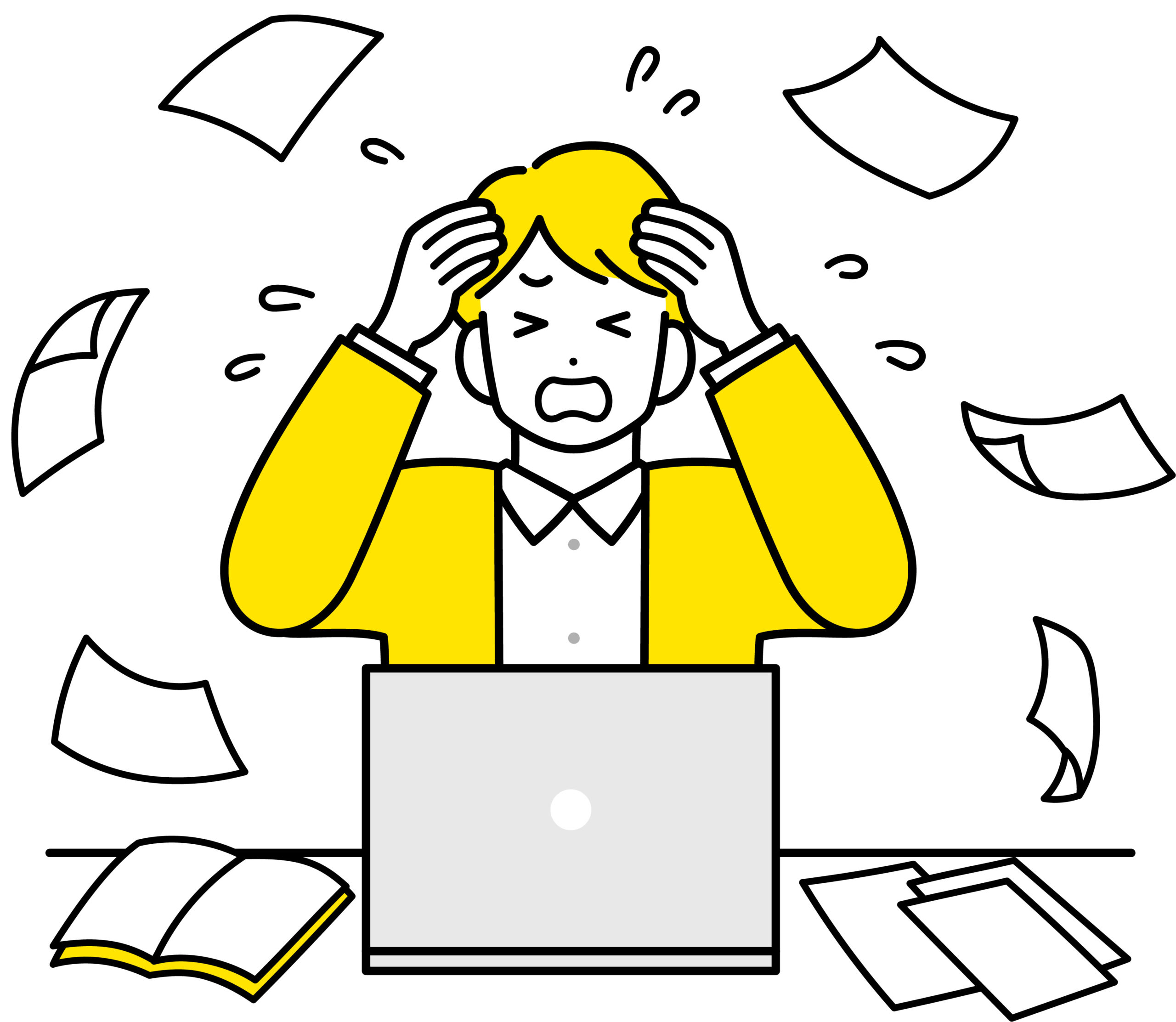
バックオフィス業務代行とは、企業の日常業務のうち、主に「裏方」として機能する事務処理や管理業務を、外部の専門業者に委託することを指します。ここでいうバックオフィスには、経理・人事・労務・総務・法務・庶務などの部門が含まれ、いずれも企業の運営を支える重要な役割を担っています。
たとえば、経理であれば請求書発行や仕訳入力、人事であれば採用事務や勤怠管理などが対象です。こうした業務は専門知識が求められる一方で、企業の収益に直結しづらい「ノンコア業務」として扱われることが多く、内製にこだわらず外注する動きが広がっています。
また、近年ではBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)という言葉でも知られ、単なる作業代行にとどまらず、業務フローの見直しや効率化までを含めた支援を提供するサービスも増えています。中小企業やスタートアップにとっては、人件費の最適化と生産性向上の両立を実現する手段として、バックオフィス業務代行が有力な選択肢となっているのです。
バックオフィス業務の範囲について
バックオフィス業務には、企業活動を円滑に進めるための多岐にわたるサポート業務が含まれます。主な領域は以下の通りです。
経理業務
帳簿作成、仕訳入力、請求書発行、売掛・買掛管理、月次・年次決算補助など。専門知識と正確性が求められるため、外部の専門スタッフに委託することでミスの防止や業務負担の軽減が期待できます。
人事・労務業務
採用活動の事務処理、雇用契約書の作成、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、年末調整など。煩雑で時期によって業務量が増減するため、代行サービスの導入で業務の平準化が図れます。
総務・庶務業務
備品管理、文書管理、来客・電話対応、社内イベント運営、社内環境整備など、組織の円滑な運営を支える業務です。属人的になりがちな業務を外注することで、担当者の負担軽減や業務標準化が可能になります。
法務・契約管理業務
契約書の作成・管理、リーガルチェック、コンプライアンス対応など。法的知識を要するため、専門性の高い業務は信頼できる外部パートナーに任せるケースが増えています。
このように、バックオフィス業務は多岐にわたり、企業規模や業種によって委託範囲も異なります。業務の棚卸を行い、自社にとって内製すべき業務と外注すべき業務を見極めることが、業務代行の成功において重要な第一歩です。
業務代行サービスが注目される背景
近年、バックオフィス業務代行サービスが急速に注目を集めている背景には、複数の社会的・経済的な要因があります。特に中小企業やスタートアップにとっては、リソースの最適化と持続可能な成長を目指すうえで、外部リソースの活用が不可欠となっています。
慢性的な人手不足
日本全体で労働人口が減少傾向にあるなか、バックオフィス部門への人材確保はますます困難になっています。経験者の採用が難しいうえに、育成にも時間とコストがかかるため、外部に業務を委託する動きが加速しています。
コア業務への集中ニーズ
経営資源をより戦略的な業務に集中させたいというニーズも大きな要因です。営業や商品開発といった「攻めの業務」に人材を集中させるため、ノンコア業務であるバックオフィス業務は外注するという考え方が広がっています。
コスト削減と固定費の変動化
社内で人員を抱えるよりも、必要な範囲で外部に委託したほうがコストを抑えられるケースもあります。特に繁閑の差がある業務においては、代行サービスを利用することで人件費を変動費化し、経営の柔軟性を高めることができます。
テレワーク・クラウド化の普及
クラウド会計ソフトやオンライン勤怠管理ツールの普及により、場所にとらわれない業務遂行が可能になりました。これにより、バックオフィス業務も物理的に社内で行う必要がなくなり、外部への業務委託がしやすい環境が整っています。
こうした背景のもと、バックオフィス業務代行は「人材戦略」「コスト戦略」「業務効率化戦略」の観点から、ますます多くの企業にとって現実的かつ有効な選択肢となっているのです。
バックオフィス業務代行のメリットと注意点
バックオフィス業務を外部に委託することで、企業はさまざまな恩恵を受けることができます。しかし一方で、導入に際しては注意すべき点も存在します。ここでは、代行サービスの代表的なメリットと、導入前に理解しておくべき注意点について解説します。
導入によるメリット
コア業務への集中が可能に
バックオフィス業務を外注することで、経営者や従業員は本来注力すべき営業・企画・開発などのコア業務に専念できます。これにより、生産性の向上や新たな価値創出にもつながります。
コストの最適化と人件費の変動化
業務量に応じて委託範囲を柔軟に調整できるため、固定的な人件費を削減し、必要な時だけコストをかける「変動費化」が実現します。特に中小企業にとっては資金効率を高める手段として有効です。
業務品質の安定化
専門知識を持つ外部のプロフェッショナルに任せることで、社内の属人化やミスを防ぎ、業務の標準化・安定化が図れます。特に経理や労務など、法的要件が絡む業務では安心感が得られます。
採用・教育コストの削減
新たに人材を採用・教育する必要がなく、即戦力を確保できる点も大きな利点です。繁忙期や急な退職などによる業務停滞リスクも軽減されます。
利用前に知っておきたいデメリット・注意点
業務範囲の明確化が不可欠
「どこまでを任せて、どこからを自社で行うか」を明確にしないまま委託を開始すると、業務の齟齬やトラブルが生じる可能性があります。契約前の業務棚卸しと合意形成が非常に重要です。
情報漏洩リスクへの配慮
社内の機密情報や個人情報を取り扱う業務を委託する以上、セキュリティ対策は必須です。プライバシーマークやISMS取得状況、データ管理体制などを確認しましょう。
社内ノウハウの喪失に注意
すべてを外注し続けると、将来的に社内で対応できる人材や知識が失われる可能性もあります。業務内容や社内体制に応じて「委託しすぎないバランス」も検討が必要です。
サービス品質にばらつきがある
代行会社によって得意分野や対応範囲、品質レベルが異なるため、事前に実績や口コミ、体制をしっかりと調査しておくことが重要です。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
バックオフィス業務代行サービスの選び方

バックオフィス業務代行サービスは多種多様で、それぞれに強みや対応範囲が異なります。自社に最適なサービスを選ぶには、いくつかの重要な視点から比較・検討する必要があります。ここでは、選定時に注目すべき3つのポイントをご紹介します。
自社に合った業務範囲・対応領域で選ぶ
まず最も重要なのが、「自社が委託したい業務」と「サービス提供側の対応範囲」が一致しているかどうかです。たとえば経理業務に特化したい場合は、会計処理や税務対応の実績が豊富な会社が適しています。一方で、総務や人事など幅広く対応してもらいたい場合は、複数の業務領域をワンストップでカバーできるサービスを選ぶ必要があります。
また、単なる業務代行だけでなく、業務フローの改善提案やクラウドツール導入支援まで対応できるかどうかも確認しておくと良いでしょう。
費用体系とコストパフォーマンスを比較する
代行サービスには、「月額固定制」「従量課金制」「初期費用+運用費」など、さまざまな料金形態があります。料金の安さだけで判断するのではなく、実際にどこまでの業務が含まれているのか、どの程度の対応品質があるのかを確認し、総合的なコストパフォーマンスで比較することが重要です。
特に中小企業の場合は、「必要な業務だけをミニマムで依頼できる」柔軟なプランがあるかどうかもポイントとなります。
実績・サポート体制・セキュリティ面の確認
実際の導入実績や対応してきた業種・規模を確認することで、自社との相性をある程度見極めることが可能です。また、日常的なやりとりをどのような形で行うのか(専任担当制・チャット対応の可否など)も、継続的な運用のしやすさを左右します。
加えて、個人情報や社内データを扱ううえで不可欠なのがセキュリティ対策です。プライバシーマークやISMS認証の有無、データの保管体制なども必ずチェックしておきましょう。
バックオフィス業務代行サービスおすすめ5選【比較表付き】
ここからは、実績・対応範囲・コストパフォーマンス・サポート体制などを総合的に評価し、おすすめのバックオフィス業務代行サービスを5つ厳選してご紹介します。
まずは、各サービスの特徴が一目でわかる比較表をご覧ください。
おすすめサービス比較表
| サービス名 | 対応業務範囲 | 特徴 | 月額料金目安 | サポート体制 |
| サービスA | 経理・人事・労務 | 専任担当制・中小企業に強い | 月5万円〜 | メール・電話・訪問 |
| サービスB | 経理特化 | クラウド会計連携に強み | 月3万円〜 | チャット・電話 |
| サービスC | 総務・庶務中心 | 小規模事業者向け柔軟プラン | 月2万円〜 | メール中心 |
| サービスD | 人事・労務全般 | 社労士常駐・法改正に強い | 月7万円〜 | 専任制・Web会議可 |
| サービスE | フルサポート型 | 業務改善コンサル付き | 月10万円〜 | 専任担当+定例MTG |
各サービスの詳細紹介
サービス①:サービスA(中小企業に最適なバランス型)
経理・人事・労務まで幅広く対応しながらも、専任担当者がつくため業務引継ぎや相談がしやすいのが特徴。中小企業や成長フェーズの企業に適しており、継続率も高い。月額5万円〜とコストバランスも良好。
サービス②:サービスB(経理特化でコスト重視)
クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)との連携に特化し、会計業務を効率的に代行。とにかく経理だけをお願いしたい、というニーズにマッチ。価格帯もリーズナブル。
サービス③:サービスC(小規模・個人事業主向け)
請求書管理や備品手配、来客対応など、いわゆる「なんでも屋」的な庶務業務にも柔軟に対応。固定費を抑えたいフリーランスや1人法人におすすめ。
サービス④:サービスD(人事・労務に強い専門型)
労働法や社会保険など法的な専門知識が求められる業務に対応可能。社労士や人事経験者が体制を組んでいるため、法改正対応やトラブル対応も安心。
サービス⑤:サービスE(コンサル付きの高機能型)
単なる代行にとどまらず、業務フローの見直しやRPA導入、SaaS活用の提案まで一貫対応。バックオフィスを抜本的に見直したい企業に最適。
バックオフィス代行サービス導入の流れ
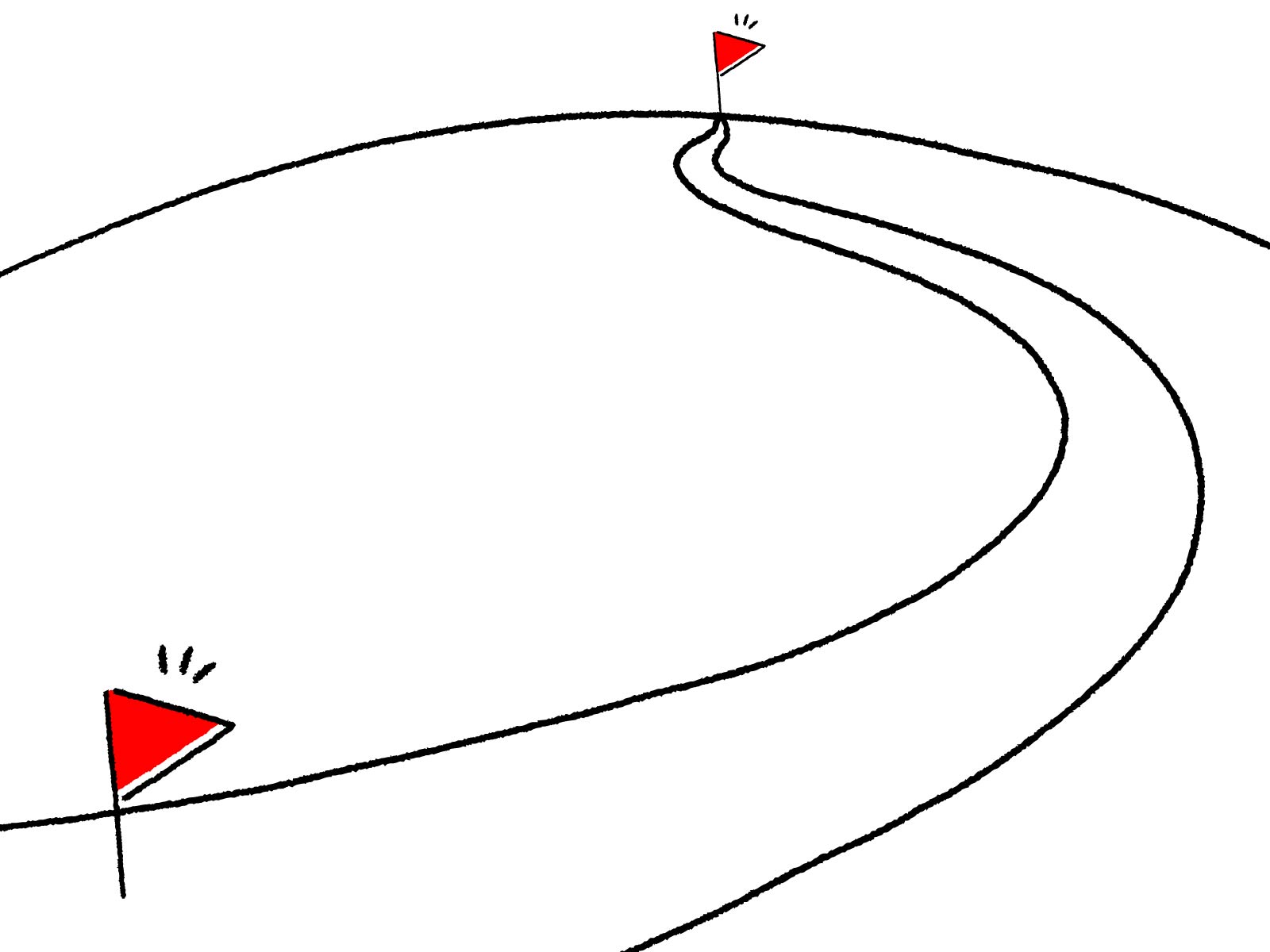
バックオフィス業務代行を導入する際は、単に「外注する」だけではなく、自社業務の可視化・整理、委託先との連携体制構築などが不可欠です。以下では、一般的な導入プロセスを4ステップでご紹介します。
ヒアリングと業務棚卸
最初のステップは、現状の業務内容と課題を明確にすることから始まります。
代行サービス側との初回ヒアリングでは、どの業務をどの範囲まで委託するか、業務量や頻度、使用中のツールなどを共有し、全体像を洗い出します。
このフェーズで自社の「業務棚卸し」がしっかりできていると、無理や無駄のない委託設計が可能になります。
契約・導入準備
業務範囲や料金、対応体制が合意できたら、正式契約へと進みます。
この際には、業務の責任範囲・納期・情報管理に関する規定(NDA含む)などを明文化しておくことが重要です。
また、導入にあたって必要なアクセス権限やツールの設定、業務マニュアルの共有など、準備作業を進めていきます。
業務移管と運用開始
契約完了後、業務の一部または全体を順次移管していきます。
初期段階では、業務の進捗確認やフィードバックを密に行い、スムーズな立ち上がりを目指します。
必要に応じて引継ぎ用マニュアルやQ&A対応などを整備し、社内と外部パートナー双方での連携を強化します。
定期的な見直しと改善提案
運用が軌道に乗った後も、定期的なミーティングやレポートを通じて、業務状況の確認・改善提案が行われます。
外注先によっては、業務効率化やコスト削減のためのプロセス改善も提案してくれる場合があります。
継続的なPDCAを意識し、より高い生産性と効果を目指すことが重要です。
まとめ|自社に合った業務代行で生産性向上を目指そう

バックオフィス業務代行は、単なる「外注」ではなく、企業経営の質を高めるための重要な経営戦略の一つです。特に人材不足やコスト圧力に直面している企業にとっては、限られたリソースを有効活用するための有力な手段となります。
本記事では、バックオフィス業務の基本や代行サービスのメリット・注意点、選び方のポイント、さらにおすすめのサービス5選を紹介しました。自社の業務内容や課題を正しく把握し、信頼できるパートナーと連携することで、業務の効率化と品質向上を両立させることが可能になります。
代行サービスの導入は、最初こそ検討や準備に時間を要しますが、中長期的には確かな業務改善効果が期待できます。自社に最適な代行サービスを見つけ、より戦略的な経営と健全な成長を実現していきましょう。
経理・人事・総務・電話対応など、プロサポXは経営者の業務負担を減らす仕組みを整えています。
単なる外注ではなく、経営者が本来の業務に専念できるよう、継続的なサポート体制を構築しています。必要な時にすぐ相談・依頼できるのが特長です。
継続的なサポート体制(LINEと専門スタッフ連携)
- LINEから業務相談や申込みが可能
- 経理・人事・総務などの代行に対応
- 依頼後も継続的にサポート&報告
依頼後も担当スタッフが継続してフォローする体制があり、初めての方でも安心して利用できます。
まずはサービス内容をチェックして、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。