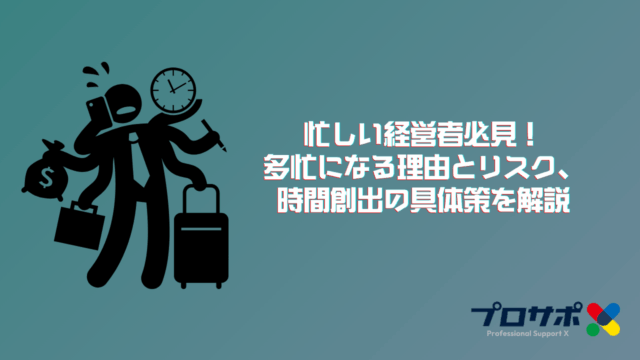バックオフィス業務が煩雑で非効率だと感じていませんか?本記事では、定型業務の見直しやITツール導入など、実践しやすい7つの効率化方法を事例付きで紹介します。時間とコストを削減し、組織全体の生産性を高めるヒントが得られます。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
すぐに使える!バックオフィス業務を効率化する7つの方法
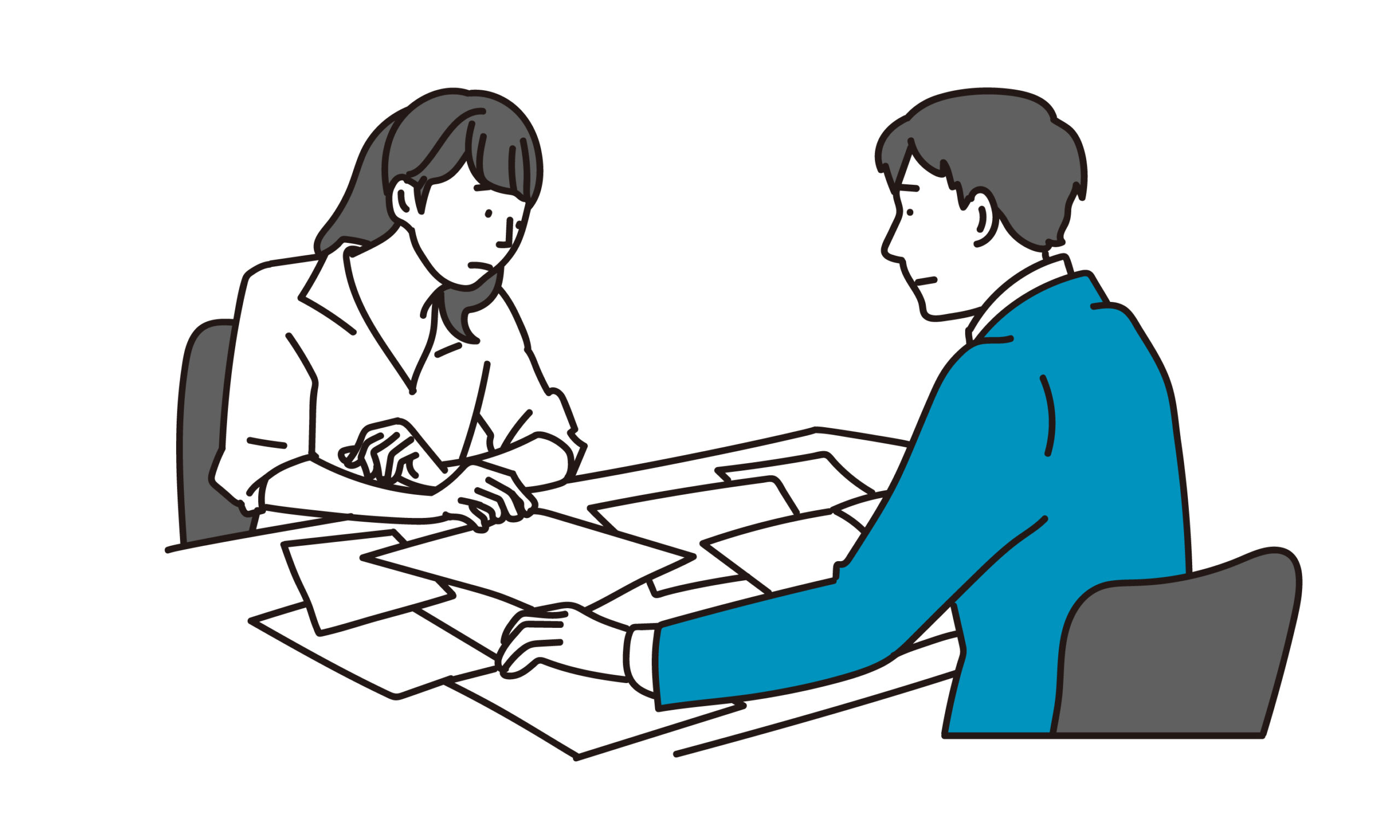
バックオフィス業務効率化の7つの方法まとめ表
| 施策 | 概要 | 導入難易度 |
| 定型業務の洗い出しと見直し | 無駄な業務や重複作業を可視化し、削減・標準化を進める | ★☆☆ |
| ワークフローシステムの導入 | 稟議・経費精算などの承認フローをデジタル化・自動化する | ★★☆ |
| RPAによる作業の自動化 | データ転記や集計などのルーチン業務をロボットが自動処理 | ★★★ |
| クラウド会計・給与ソフト導入 | 経理・労務業務をクラウド上で効率的に処理し、人的負担を軽減する | ★★☆ |
| 社内情報の共有・管理の最適化 | 社内Wikiやストレージを活用し、資料探しやナレッジ共有を効率化する | ★☆☆ |
| 業務のアウトソーシング(BPO) | 専門的なバックオフィス業務を外部に委託して社内負担を減らす | ★★☆ |
| 人材配置と役割分担の見直し | スキルに応じた業務配置や兼務体制で社内リソースを有効活用する | ★★☆ |
※導入難易度は一般的な中小企業を想定した目安です。環境や体制により変動します。
すぐに使える!バックオフィス業務を効率化する7つの方法
1.定型業務を洗い出して無駄を削減する
まず取り組みやすいのが、日々の定型業務を棚卸しして、非効率な作業を見つけ出すことです。帳票の二重出力、Excelの転記作業、承認待ちの停滞などは、属人化や過去の慣習から継続されているケースも少なくありません。現場担当者の声を聞きながら「本当に必要な業務かどうか」を見極めると、改善のヒントが見えてきます。
業務の見える化によって、手戻りや重複を防ぎ、シンプルな手順で成果が出せる仕組みに変えていくことが、効率化の第一歩です。導入のハードルが低く、即日実施できる点も魅力です。
2.ワークフローシステムで申請・承認を自動化
紙ベースで行われている申請・承認業務は、時間がかかるうえに、管理が煩雑になりやすい領域です。クラウド型のワークフローシステムを導入すれば、稟議、経費精算、休暇申請といった日常的な手続きがオンライン上で完結し、承認のスピードも格段に上がります。
以下のような効果が期待できます。
- スマホやPCからいつでも申請・承認が可能になる
- 申請内容や履歴が自動で蓄積・管理される
- 書類の紛失や確認ミスを防げる
初期設定にはやや手間がかかるものの、一度運用が軌道に乗れば業務負担は大幅に軽減されます。
3.RPAで単純作業を自動化する
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、人が行っていた繰り返し作業をソフトウェアに任せる仕組みです。特に、フォーマットの決まったデータ入力や、月次の請求処理などはRPAとの親和性が高く、導入効果が出やすい業務といえます。
たとえば次のような場面で活用されています。
- 見積データを会計システムに自動転記
- 毎月の給与データをフォーマットに沿って自動集計
- 取引先からの注文内容を販売管理システムに自動登録
RPAの導入には専門的な設定や初期投資が必要ですが、適切な業務を選べば月数十時間単位の業務削減が可能です。
4.クラウド会計や給与ソフトを導入する
経理や給与計算においても、クラウドサービスの活用は効率化の鍵となります。たとえばクラウド会計ソフトでは、銀行口座との連携により明細が自動取得され、仕訳処理もAI補助でスピーディーに完了できます。また、給与ソフトでは、法令改正に即した対応や自動計算が可能なため、年末調整や月次給与処理の手間が大きく削減されます。
これらのツールは中小企業でも導入しやすい価格帯が多く、操作性もシンプルに設計されています。紙やExcel中心だったバックオフィスが、クラウド化によって業務ミスや処理漏れのリスクを減らせるようになります。
5.社内情報の共有・管理を効率化する
社内の資料や業務ノウハウが個人のPCやメールに散在していると、情報共有に時間がかかるだけでなく、引き継ぎ時にも混乱が生じます。そこで有効なのが、社内Wikiやファイル共有ツールの活用です。
導入時の工夫としては以下のようなポイントが挙げられます。
- 各部署の資料を1つのクラウドストレージに統一する
- 業務マニュアルを誰でもアクセスできる社内Wikiに掲載
- フォルダ構成や命名ルールを明文化し、検索性を高める
これにより情報の属人化を防ぎ、新人教育や引き継ぎの効率化にもつながります。
6.業務の一部をアウトソーシングする
業務の一部を外部に委託することで、社内の人手不足を補いながら、専門的な品質を担保することができます。経理記帳、給与計算、社会保険手続き、電話対応などは、外注しやすく効果も出やすい分野です。
アウトソーシングを検討する際には、以下の点を見極める必要があります。
- 委託先の実績や専門性(業界に特化しているか)
- セキュリティや契約条件の明確性
- 自社内で必要なコントロール体制を維持できるかどうか
うまく活用すれば、コスト削減と同時に社員の負担を減らし、戦略的な業務へ集中できる環境を整えられます。
7.人材配置と役割分担を見直す
最後に重要なのが「人の最適配置」です。同じ業務でも、適性のある人が担当することで作業スピードや品質が大きく変わるため、人材の持ち味を活かした役割分担が不可欠です。
具体的には、社員一人ひとりのスキルや得意領域をマッピングし、業務の偏りや属人化を解消するアプローチが有効です。兼務やローテーション制度も取り入れることで、柔軟な体制を築くことができ、リスク分散や育成にもつながります。
プロサポXでは、経理・人事・総務といった日常業務を専門チームがサポートし、経営判断や戦略に専念できる体制を構築します。
まずはLINEでサービス内容をチェックし、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。
効率化を成功させるために意識すべきポイント

現場の声を吸い上げる
バックオフィスの効率化は、単に仕組みやツールを導入するだけでは成功しません。重要なのは、実際に業務を担っている現場の声を反映させることです。
担当者の業務フローや悩みをヒアリングすることで、「見えづらい無駄」や「本当に必要な作業」が明らかになります。トップダウンではなく、現場発信の改善提案を尊重することで、スムーズな導入と定着につながります。
また、現場の協力を得るためにも、「なぜその効率化が必要なのか」を丁寧に説明し、納得感のある進め方を意識することが大切です。
段階的に導入・改善を進める
効率化の取り組みは、一度にすべてを変えようとすると現場に負荷がかかり、かえって混乱や反発を招くことがあります。だからこそ、優先順位をつけて、段階的に導入していくアプローチが有効です。
以下のようなステップで進めるとスムーズです。
- 緊急性・重要性の高い業務から着手する
- 小さな改善を積み重ね、成果を可視化する
- 成功体験を共有し、他部署へ水平展開する
このようにスモールスタートで進めることで、従業員の心理的ハードルも下がり、着実に定着させることができます。
数値で効果を可視化する
効率化の取り組みが進んでいるかどうかは、感覚ではなく数値で判断することが重要です。たとえば「処理時間の短縮」「工数削減」「人的リソースの再配置」「ミスの削減数」など、定量的な指標をあらかじめ設定しておきましょう。
KPI(重要業績評価指標)を設定して効果を可視化することで、経営層への報告や次の改善判断がしやすくなります。また、改善による成果が明確になれば、現場のモチベーションや協力意欲の向上にもつながります。
まとめ

バックオフィス業務の効率化は、日々の業務を支える組織基盤の強化につながります。本記事で紹介したような「定型業務の見直し」や「RPA・クラウドツールの活用」、「人材配置の工夫」などは、どれも中小企業でも実践できる現実的な施策です。
取り組む際は、現場の声を反映させながら段階的に進め、数値で成果を可視化することが成功のカギになります。すぐに取りかかれる内容から少しずつ着手し、時間とコストのロスを減らしていきましょう。
自社に合った効率化施策を選び、バックオフィス業務を経営の強みに変えていく。
その第一歩は、今できる「ひとつの改善」から始まります。
経理・人事・総務・電話対応など、プロサポXは経営者の業務負担を減らす仕組みを整えています。
単なる外注ではなく、経営者が本来の業務に専念できるよう、継続的なサポート体制を構築しています。必要な時にすぐ相談・依頼できるのが特長です。
継続的なサポート体制(LINEと専門スタッフ連携)
- LINEから業務相談や申込みが可能
- 経理・人事・総務などの代行に対応
- 依頼後も継続的にサポート&報告
依頼後も担当スタッフが継続してフォローする体制があり、初めての方でも安心して利用できます。
まずはサービス内容をチェックして、業務負担の軽減に向けた第一歩を踏み出してください。
サービス紹介ページからLINE登録も可能です。